出てから駆除じゃ遅すぎる!?シロアリの予防法7選
–家づくりはカタログ一括請求から始めよう!–
本文に入る前に、マイホームを考えているあなたに向けて重要なことをお伝えします。
マイホーム作りでまず初めにやらなければいけないこと、それは「住宅メーカー選び」です。
土地探しよりも、資金調達よりも、まず初めに住宅メーカーを探すことが大事。というのも、依頼する住宅メーカーに関して後悔する声が後を絶たないからです。
建てた後に後悔してしまわないように、初めの段階でメーカーの比較を十分に行っていきましょう。
「でも全国各地に無数にある住宅メーカーからどれを選べばいいかわからない」
という問題が出てきますよね。
そこで活用してほしいおすすめサービスが、東証一部上場のリクルートが運営するカタログ一括請求サービスです。
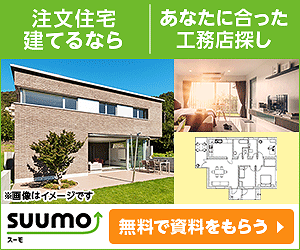
カタログ一括請求サービスを利用すれば、条件に合うおすすめ住宅メーカーのカタログが一括で届きます。しかも無料。
予算や住宅のテーマ、シニア向けやエコ住宅などの条件を選択できるので、あなた好みの住宅メーカーを探すことが可能です。
ぜひ一括請求で理想のハウスメーカーを探してみてくださいね!
SUUMOでカタログを一括請求してみる⇒
知らぬ間に床下から侵入し、家屋の木材やプラスチックまで食べてしまうシロアリ。
気づいた時には、すでに家中ボロボロという事態にもなりかねません。
そうならないためにも、シロアリの予防策は事前に立てておきたいですね。
新築時に対策をしておくのが理想ではありますが、建ててからでも予防することはできます。
リフォームは一括見積もりがおすすめ!
本文に入る前に、家のリフォームをお考えの方にぜひ知っておいて頂きたいことをお伝えします。
リフォームを検討する際は、必ず早い段階で事前に何社かに見積もりをとって下さい。
というのも、リフォームは料金も技術も会社によって大きなバラツキがあります。
折込チラシやホームセンター、近所の会社で決めてしまい10万円、中には100万円以上の損をしまう方は非常に多いです。
そうはいっても
「リフォームは専門用語や相場も分かりにくし、どの会社に相談したら良いか分からない」
と思っている方も多いですよね。
そこで活用して欲しいのが、リクルートが運営するsuumoカウンターリフォーム。
スマホからいくつかの質問を選択すると、あなたの条件にあった会社を3-4社ピックアップしてくれます。
☆厳しい審査をクリアした優良会社のみ
☆無理な営業は一切なし
☆お断り代行してくれるので安心
☆無料で事前相談だけでもOK
3-4社に見積もりを出してもらうことで相場も知ることができます。
また、競合させることで料金が下がる可能性が高くなるのも大きなメリットの1つです。
無理な営業を受けることもありませんよ。
スマホからかんたんに出来るので、リフォーム検討中の方は今すぐチェックしておくことをおすすめします!
SUUMOカウンターリフォームへの申し込みはコチラから⇒
このページの目次
1.侵入を防ぐのが最も大事
シロアリ予防にとって最も重要なのはその侵入を防ぐことにあります。
湿気が多く暗い場所に、木材という餌があれば彼らが侵入をあきらめることはありません。
シロアリは建物の下からやってくることが多いので、家屋の基礎工事が重要なポイントになってきます。
基礎工事においては、地面をコンクリートで覆う工法(ベタ基礎)が効果的ですが、コンクリートの経年劣化等によるひび割れ箇所からの侵入も考えられるため、定期的なメンテナンスを忘れずに行いましょう。
さらなる対策強化として、土台の下部に金属板を敷いて、シロアリが入り込めないようにバリアをしてしまう手法や、基礎パッキンや換気口の部分に目の細かなステンレス製の網を張る「ターミメッシュ工法」などがあります。
いわゆる物理的に壁をつくって防ぐ方法は、対策としては最低限のものと言えます。
2.湿気対策も考えよう
餌となる木材を求めてやってくるシロアリは、湿気のある場所、光の入らない場所、通気のない場所を好む傾向があり、そのすべてが整っている床下は、彼らにとって最高の環境といえます。
湿気によって木材が腐ってくると、シロアリを呼び寄せてしまう可能性も高くなります。
【簡単1分】SUUMOで無料カタログを取り寄せる⇒
通気をよくして乾燥させるだけでもシロアリ対策には効果的なので、できるだけ湿気がこもらない環境を心がけましょう。
床下が高かったかつての住宅と異なり、現代の家屋は前述のベタ基礎などの工法により湿気のこもりやすい設計が主流です。
シロアリの侵入を防ぐことさえできていれば問題はありませんが、一度、蟻道(ぎどう。アリの通り道)ができてしまうと格好の住処となってしまうというデメリットもあります。
床下に換気扇をつけてカビやダニの発生を防ぐ処理や、防湿シートを敷いた上に調湿材(炭やゼオライトなど。湿気を吸ったり放出して自然な湿度を保つ作用がある)を撒くという方法もあります。
最も重要なのはシロアリの侵入経路を防ぐことで、さらなる対処として湿気対策も行えるとよいでしょう。
3.シロアリの存在に気づこう
シロアリの存在に気づけることが、ある意味最も予防につながります。
梅雨前から梅雨時にかけて「飛んでいるシロアリ」が大量に出たりすると分かりやすい(アリは群れが一定数以上に増えると羽アリになっていく)のですが、そうなる前であれば地面からやってきます。
現代の家屋は、床下のスペースを省略していたり、低すぎたり、設計が複雑だったりと、なかなか床下に潜っての対策が難しいケースが増えています。そのため、シロアリの存在に気づくのが遅れてしまうのです。
地面に最も近い玄関がシロアリの被害を受けやすい部分になっていますので、日頃から変化に気づけるよう注意しておきましょう。
4.シロアリが嫌いな木材を選ぼう
シロアリが家屋の木材を食べてしまうことで被害が起こります。
基本的に、シロアリが好むのは木材のやわらかい部分です(そのため、外側から年輪に沿ったように食べられることが多いです)。
つまり硬い木材を使用すると、それだけシロアリ被害を受けにくくなるということです。
シロアリに食べられにくい種類の木材も存在します。
例えば、カシやヒバ、スギ、ヒノキといった品種は食害を受けることが少なくなります。
逆に、被害を受けやすいのはモミやトウヒといったホワイトウッドです。
家を建てる際には、木材の選択にも注意を払いましょう。
芯材(木の中心部)で、しかも高樹齢のものであるほど食べられにくくなります。
たとえヒノキであっても、辺材を使っているのであれば、そこは柔らかく、シロアリの餌になってしまいます。
5.木部処理でシロアリ予防
たとえ、シロアリに好まれるような柔らかい木材でも、木部処理を施すことによって被害を抑えることができます。
木部処理とは、シロアリ被害の可能性がある部材に防蟻用薬剤を吹き付けたり注入したりする事を指します。
これによってシロアリがその木材を避けるようになります。
注入の場合は、ドリルによって木材に穴を開け、そこから薬剤を入れていきます。
穴には木栓をするので、薬剤がしっかり木に染み渡ります。
そのため、定期的に木部処理を行うことで、被害を抑えることができます。
一般的に、地面より1メートルほどの高さまでの部材が対象になります。
それ以外にもキッチンやお風呂場などの水回り付近にある木材に対しても処理を行うことがあります。
既存の家屋に対しては、予防的な意味合いで実施することもありますし、すでに食害がある際にシロアリを追っ払うために行う事もあります。
6.土壌処理でシロアリ予防
薬剤での対策は、木部のみに限りません。シロアリがやってくるであろう土壌に対しても処理を行います。
基礎工事の際に土壌部分に土壌処理剤を散布しますが、これはコンクリートで地面を覆った時も同様です。コンクリート面に土壌処理することで、よりシロアリを寄せ付けなくなります。
特にイエシロアリやヤマトシロアリといった種類は地中からやってくることが多く、土壌処理は有効な対策になります。
木部処理と土壌処理で使われる薬剤は別になります。
ただしどちらも薬の効果は数年といったものが多いのです。
前回の処理から5年以上が経過していたら、新しく処理を施す事も考えましょう。
防蟻剤の種類は様々で、シロアリを殺す効果があるものや、木材を食べられにくくするもの、シロアリが嫌がる成分を出すものがあります。
ただし、薬剤によっては大量に使用すると人体への影響も懸念されるため、対処の際には業者とよく相談しておきましょう。
特にアレルギーがある方は要注意です。
7.ベイト工法 でシロアリ予防
薬剤を撒くことをせずに、防蟻を行う手法がベイト工法になります。
これはシロアリの習性を上手く利用し、ベイト剤という毒の餌によってシロアリ防除を行います。
ここで使われるベイト剤は、散布用の液剤と異なり、ごく少量のもので大丈夫です。
やり方としては、シロアリの餌となる木を容器(ステーションという名前です)に入れて、家屋や周辺のあちこちに設置します。
点検を定期的に行い、木が食べられている箇所(=シロアリが出現している)に、ベイト剤を設置していきます。
シロアリは毒であることを知らずに、このベイト剤を巣に持ち帰ります。
シロアリは仲間同士で体をなめあうグルーミングを行うため、遅効性の毒であるベイト剤がどんどんシロアリ同士に行き渡り、数か月もすると彼らのコロニーが死滅する、という手法です。
ただし、食害をしている木の内部にコロニーを形成しているシロアリや、分散して形成しているシロアリには効果が薄くなります。
シロアリは家屋を管理する方にとっては恐ろしい存在ですが、予防法を知っておけば被害を最小限に抑えることができます。
建築時にシロアリへの予防を実施しているかどうかは、その後の家屋の運命を左右します。
費用や労力、環境も考えて、適切な予防法を選びましょう。
⇒おすすめのシロアリ駆除業者はこちら
【簡単1分】SUUMOで無料カタログを取り寄せる⇒

