建蔽(ぺい)率とは

–家づくりはカタログ一括請求から始めよう!–
本文に入る前に、マイホームを考えているあなたに向けて重要なことをお伝えします。
マイホーム作りでまず初めにやらなければいけないこと、それは「住宅メーカー選び」です。
土地探しよりも、資金調達よりも、まず初めに住宅メーカーを探すことが大事。というのも、依頼する住宅メーカーに関して後悔する声が後を絶たないからです。
建てた後に後悔してしまわないように、初めの段階でメーカーの比較を十分に行っていきましょう。
「でも全国各地に無数にある住宅メーカーからどれを選べばいいかわからない」
という問題が出てきますよね。
そこで活用してほしいおすすめサービスが、東証一部上場のリクルートが運営するカタログ一括請求サービスです。
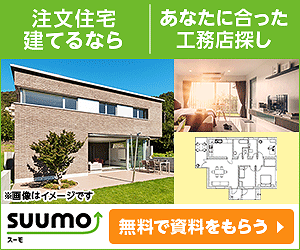
カタログ一括請求サービスを利用すれば、条件に合うおすすめ住宅メーカーのカタログが一括で届きます。しかも無料。
予算や住宅のテーマ、シニア向けやエコ住宅などの条件を選択できるので、あなた好みの住宅メーカーを探すことが可能です。
ぜひ一括請求で理想のハウスメーカーを探してみてくださいね!
SUUMOでカタログを一括請求してみる⇒
防火面と住環境への配慮面などから、土地には各種の規制がかけられることがあります。エリアによって異なりますが、都市計画で定められた用途地域により敷地面積に対しての建築面積割合が設定されており、これを「建蔽(ぺい)率」と呼びます。
【簡単1分】SUUMOで無料カタログを取り寄せる⇒
リフォームは一括見積もりがおすすめ!
本文に入る前に、家のリフォームをお考えの方にぜひ知っておいて頂きたいことをお伝えします。
リフォームを検討する際は、必ず早い段階で事前に何社かに見積もりをとって下さい。
というのも、リフォームは料金も技術も会社によって大きなバラツキがあります。
折込チラシやホームセンター、近所の会社で決めてしまい10万円、中には100万円以上の損をしまう方は非常に多いです。
そうはいっても
「リフォームは専門用語や相場も分かりにくし、どの会社に相談したら良いか分からない」
と思っている方も多いですよね。
そこで活用して欲しいのが、リクルートが運営するsuumoカウンターリフォーム。
スマホからいくつかの質問を選択すると、あなたの条件にあった会社を3-4社ピックアップしてくれます。
☆厳しい審査をクリアした優良会社のみ
☆無理な営業は一切なし
☆お断り代行してくれるので安心
☆無料で事前相談だけでもOK
3-4社に見積もりを出してもらうことで相場も知ることができます。
また、競合させることで料金が下がる可能性が高くなるのも大きなメリットの1つです。
無理な営業を受けることもありませんよ。
スマホからかんたんに出来るので、リフォーム検討中の方は今すぐチェックしておくことをおすすめします!
SUUMOカウンターリフォームへの申し込みはコチラから⇒
100坪の敷地に30坪の家が建っているなら―建蔽(ぺい)率は30%
敷地面積に対しての建築面積を建(ぺい)率と呼びます。そのため、見出しに挙げたように100坪の敷地に30坪の建物が存在すれば、それは建蔽(ぺい)率30%となります。この計算式に用いられる数字は、あくまでも建築面積で、延べ床面積ではありません(※延べ床面積を用いると“容積率”となります)。
単純に考えたなら、建蔽(ぺい)率70%と定められた土地があったのなら、30%は周囲との距離を保つべきスペースに使用しなければならない、ということです。
逆引き的に考えてみましょう。ある土地に、四方をぐるりと犬走り程度の空間を設けただけの家を建てたとした場合、建蔽(ぺい)率は60%~70%となります。せっかくの一戸建てならば、むしろ建蔽(ぺい)率のハードルは低めでもよいのかもしれません。より長時間の日照や風の通りを確保したい、ちょっとでも庭が欲しいというご希望はないでしょうか。(※生活に必要なスペースは、容積率で稼ぎ出すプランを練ります)
建ぺい率はどうやって決まる?
建ぺい率は、都市計画によって定められた用途地域によって決まります。第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域ならば、30%~60%までのいずれかです。第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域ならば、50%~80%までのいずれかとなります。
市街地から車や電車で30分も離れると、街並みのイメージが「縦」から「横」へと変化するのは、この都市計画によって定められた用途地域が影響しているからなのです。用途の混在を防ぐことを目的とした用途地域は、将来の都市のあり方をプランニングし、健全なまちを維持するために必要な決め事です。
緩和措置が採られるケースも
用途地域とプラスして防火地域の指定を受けている土地で、耐火建築物を建てる場合、10%~の緩和を受けることのできるケースがあります。また、角地では一定の条件を満たした場合、10%の上乗せを認めることもあります。建築許可を下す自治体(特定行政庁)によって判断はまちまちですので、個々に指導や判断を受けることとなります。
これは、専門家である建築家のテリトリーですので、与えられた条件下で最善のプランを立ててくれるはずです。
【簡単1分】SUUMOで無料カタログを取り寄せる⇒
